今回は公認会計士の最終関門である
修了考査の制度
について解説します。
まず修了考査を受けるのが難しい
そして最近は修了考査自体も難しいという
長く険しい道を経て
会計プロフェッショナルになっていくのです。
修了考査までの道のり
公認会計士試験は
①短答式試験
②論文式試験
~2年以上の実務経験・3年間の補修所~
③修了考査
という構成になっています。
論文式試験に受かってから、
原則として3年後に修了考査を受ける、
ということですね。
世の中がいう公認会計士試験とは
②論文式試験までです。
意外と最終関門については触れられていません。
②論文式試験までのお話はこちらから
修了考査前後での肩書の違い

修了考査合格前は
「公認会計士試験合格者」
「公認会計士協会準会員」
修了考査合格後は
「公認会計士」
「公認会計士協会正会員」
となっています。
通常、名刺にこの肩書がそれぞれ掲載されます
「公認会計士試験合格者」も
一連の説明を他人にするのが煩わしいので
業界外の人と話すときは「公認会計士」と
言っちゃったりします。
修了考査の受験資格
①2年以上の実務経験
②補修所で所定の単位数を得る
この2点です。
実務経験については最悪2年間ぼーっとしてても満たせますが
補修所では3年間を通して
・200時間前後の講義の受講
・全10回の試験(4割未満足切り+平均6割の得点が必要)
・グループディスカッション
・レポート5回(4割未満足切り+平均6割の得点が必要)
が必要となっており、
予想外にしんどいです。
試験の単位が足らず、
15,000円の追試代を何度も支払って
単位を満たしている人もいますし、
単位要件を満たせず、
修了考査を受験することすらできない人が
毎年何人もいます。
監査法人においては
受験が遅れると、昇進が遅れたり
評価が下がることでボーナスにも影響します。
試験制度に理解のある監査法人等では
補修所に行く時間を気にかけてくれたりしますが
仕事が多忙だったり、一般事業会社勤務の人は
なおのこと受験資格を得るのは厳しいといえます。
修了考査は難しい
修了考査が難しいとは言いつつも、
・受からなければ話にならない
・上司はもちろん全員合格している
ことから
「まぁ専門家なら受かって当たり前っしょ」
という空気がかなりあります。
全くもってその通りなんですが
難しいものは難しい….
次回の記事では難易度について
解説していきます。
ここ2年で合格率は激減しました。


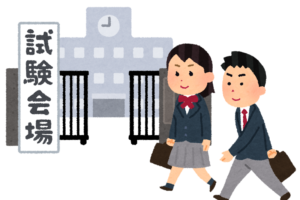









コメントを残す